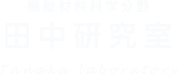.jpg)
こんにちは。共同研究員の山田と申します。徐々に寒くなってきて、鍋が美味しい季節になりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。
私は社会人として歩み始めて3年半が経ちました。仕事柄専門性を磨くことはもちろん大切ですが、私が個人的に最重要課題だと感じているのがコミュニケーション力です。そんなコミュニケーションに対する自分自身の変化を等身大で振り返ってみようと思います。
学生時代の研究活動は、ほとんどが研究室の中で完結していました。実験や解析は自分で試行錯誤し、得られた結果をもとに先生や共同研究者と議論するスタイル。専門性が高く、設備も先生方のサポートも充実していたためです。狭く深いつながりの中で、じっくりと“個”に向き合う時間が多かったように思います。
会社に入ると、それまでとは全く違う世界が広がっていました。関わる人の数・幅は桁違いに増え、関連する技術も多種多様になりました。自分の知識や経験だけでは足りないことばかりで、部署内外の多くの方に相談しながらテーマを進めます。納期を優先して評価・解析を依頼したり、サプライヤの方と面談したりと、社外の関わりも増えました。限られた時間の中で様々な立場の方と意思疎通を図る必要がある一方、忙しい相手の時間を奪っている?伝えたいことが伝わっていない?一方的な押し付けになっている?といったもどかしさが募り、苦手意識は強まっていました。
そのような中、田中研に駐在する機会をいただきました。会社とは異なる環境で、助言をくれる部署の先輩も近くにいない状況です。共同研究員の立場だからこそ、自ら動き、積極的に声をかけることが求められます。最初は戸惑いもありましたが、過ごしていくうちに自然とコミュニケーションへの抵抗感が薄れていったように感じます。そして、会話を大事にして協力を仰ぎオープンに取り組めると、テーマが加速することを実感しました。
ただ、それまで意識が自分の内側に向いていただけで、会社でも田中研でも周りは懇切丁寧に相談に乗ってくださる方ばかりです。その恩恵を最大限受け取り生かすために、伝え方、聞き方、巻き込み方などが必要になってきます。周りの方を見ていて真似したいなと思うのは、例えば、雑談するかのように相手のやっていることを聞いて自分のテーマに活用できる部分がないか考えたり、結論を急がずに相手の考えを聞き出す質問を遠くから投げかけたり、、直球ではないコミュニケーションで全体像を作り上げていく技ですね。他にも沢山あります。周りの方を盗み見て実践していきたいと思います。