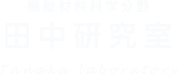こんにちは、共同研究員の柳澤です。私はリチウムイオン電池(LIB)向けの「バインダー」──LIB内で主に材料同士を接着する役割を担うポリマー材料──の研究開発をしています。少し前の話になりますが、中国へ出張した際のことについてお話します。この出張では、上海から常熟を経由し、最終的に深圳を訪れました。深圳といえば、BYDやテンセント、ファーウェイといった世界的な企業が生まれた地であり、「中国のシリコンバレー」とも呼ばれる都市です。
深圳では、世界最大級の二次電池展示会「CIBF2025」に参加しました。この展示会には、3000社以上の企業が出展し、3日間で延べ40万人以上が来場しており、そのスケールの大きさに圧倒されました。日本で開催される展示会と比べて5倍以上の規模であり、非常に活気に満ちていました。また、日本の展示会ではあまり見られない光景として、中国の企業が自社の技術や情報をオープンに話す姿勢が印象的でした。秘密保持よりも、他社と協業して新しい価値を生み出そうとする意欲が強く感じられ、非常に刺激を受けました。
LIBの多くは新エネ車(BEV, PHEV)に利用されていますが、中国の道路を眺めた際の新エネ車割合も非常に印象的でした。中国では新エネ車は緑色のナンバープレートを付けており、その割合は上海で3割程度、深圳で7割程度、CIBF会場付近では8割から9割という状況でした。ニュース等でよく聞く話ではありましたが、やはり「百聞は一見に如かず」であり、日本との大きな違いに驚かされました。(運転マナーも日本とは大きく違っていましたが……)また、自動車以外にも多くの電気スクーターが街中を走っており、電動モビリティが生活に根付いている様子が伺えました。
LIBはソニーが世界で初めて製品化に成功したという歴史があり、二次電池分野はこれまで日本が世界をリードしてきました。しかし、日本の基礎研究レベルは依然として高いものの、いまや二次電池分野の中心が中国であることは疑う余地もありません。再び日本が世界をリードするためには、中国の優れた部分(スピーディな他社との協業など)を学び、吸収し、そして日本全体で研究開発を進める必要があるのではないかと考えさせられた中国出張でした。
大学での共同研究についても触れておきたいと思います。大学は、産業界とは異なる視点で研究を進めることができる貴重な場です。企業では短期的な成果や実用化が重視される傾向がありますが、大学では基礎研究や長期的な挑戦的テーマに取り組むことが可能です。私が研究しているLIB向けのバインダー材料も、基礎的な物性の解明や新しいポリマー設計など、自社では行わないアプローチを田中研・そしてCREAプロジェクトで進めています。
世界の技術革新のスピードは非常に速く、日本が再びリードするためには、産学官が一体となって研究開発を進める必要があります。私自身も、大学での研究活動を通じて、日本の技術力向上に少しでも貢献できるよう、これからも努力を続けていきたいと思います。